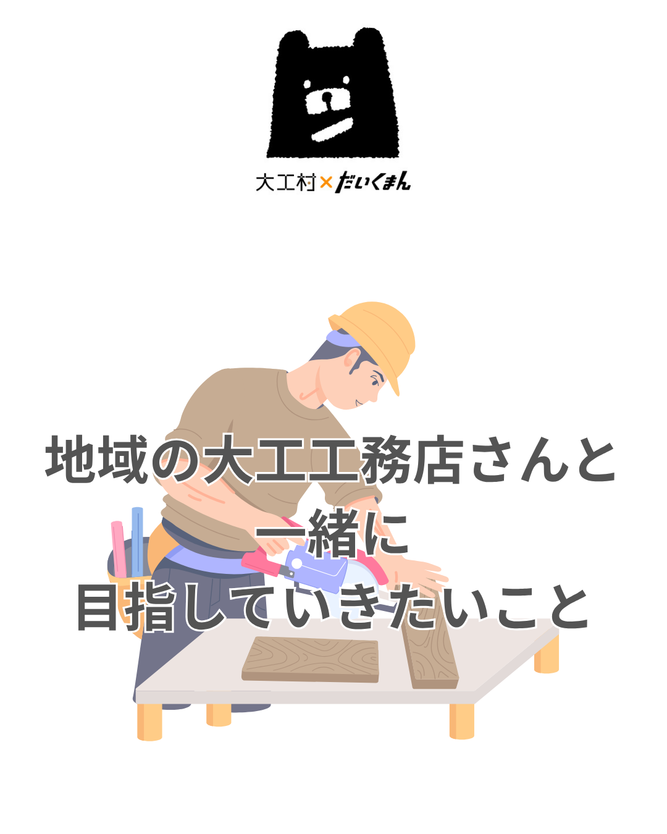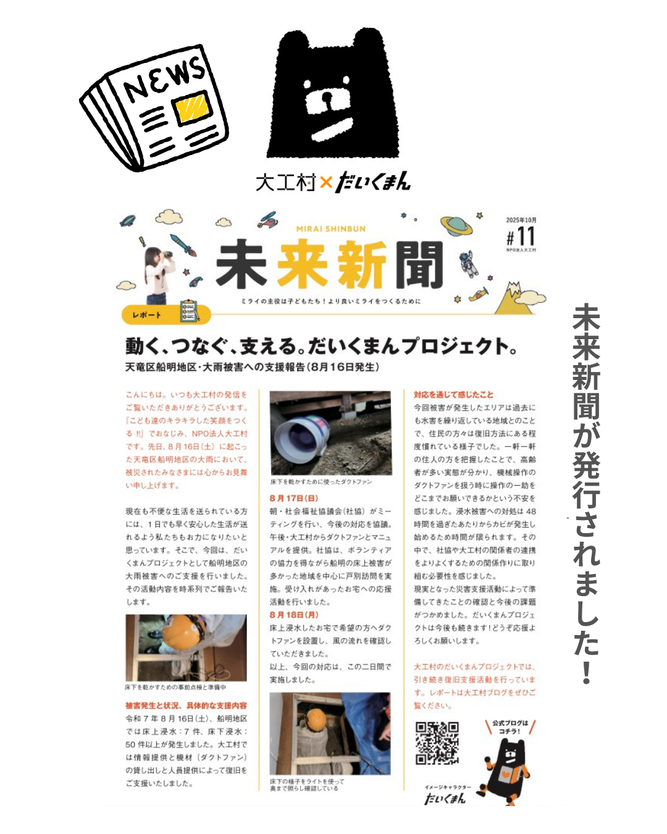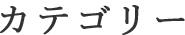こんにちは
いつも大工村の発信をご覧いただきありがとうございます。
『こども達のキラキラした笑顔をつくる!!』でおなじみ、NPO法人大工村です。
NPO法人大工村サイトはこちら♪
だいくまんプロジェクトのサイトはこちら♪
前回は、水害被害の復旧活動のための助成金活用のご報告をさせていただきました。現場で作業にあたること以外にも、だいくまんプロジェクトは日常からできることをコツコツと進めています。その一つが、復旧活動の実働を一緒に担っていただく社会福祉協議会の方との交流です。
現在、もしも次に災害が発生したらという危機意識の共有とともに、現場での動きのシミュレーションなど、体験者だから分かち合える内容を中心に、鹿児島県霧島市(小浜ビレッジ)と静岡県菊川市の社会福祉協議会のみなさん(https://kiku-syakyou.or.jp/business/disaster/)でWEB会議を計画をしています。(会議は来年早々に行う予定)
会議では、お互いの復旧支援活動の報告会という位置付けとし、不幸にも復旧活動をすることになった我々静岡県西部の社会福祉協議会の方と「発災(被害が発生すること)後の動きをどうするか?」というリアルな投げかけへのやりとりに時間を割きたいと思っています。その中でも会議で意見交換したいテーマがマニュアルの必要性です。只今、私たちはマニュアル作りに着手しておりこの年末年始にかけてまとめていく予定です。
現在大工村のだいくまんプロジェクトは大学教授である中谷先生に技術顧問として連携していただき、まずは水害復旧の活動を中心に進めています。災害の被害普及に携わると、水害、地震などそれぞれに対応の仕方の違いがあり、大変奥深いものと感じています。
自然や人間と向き合う取り組みは、常に尊さを感じつつ、意識には真剣さが必要ではないかと痛感することばかりです。安全な暮らしのありがたさを感じながら、「発災(被害が発生すること)後の動きをどうするか?」という危機意識を他の地域の方と共有しながら、学びを深めていく活動へとつなげていきたいと思います。