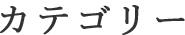ようこそ、大工村へ!
家づくりをご検討中の皆さまは、「大工さんに家を建ててもらおう」と考えたことはありますか?考えたことがあるという方も、「一体、大工さんに頼むって、どういうことなんだろう?」と思いませんか?
今回は、「大工さんに頼むって、どういうことなの?」という疑問にお答えしたいと思います!
実は、大工さんはたった一人で家を建てるわけではないんです。家づくりを取り仕切る棟梁として電気屋さん、防水屋さん、クロス屋さん、ペンキ屋さん、左官屋さん、鳶職人さんなどの家づくりの専門職人さんたちと協力して家を完成させます。
こういった職人さんたちとは大工村のイベント「こども工務店」等で皆さんも会うことができますよ。

大工村に入村している大工さんたちは、建築会社を経営していたり、地元の腕のいい職人さんたちと連携を取って協力し合っていたり、営業形態は様々ですが信頼できる大工さんばかり。
大工さんも職人さんたちも、遠州地域で活躍している方たちばかりですので、建てた後のことも安心して家づくりを任せることができますよ!
大工さんにいきなり連絡するのは気が引ける......という方は、お施主さんと大工さんのマッチングサイト「大工村.com」をぜひご利用ください。
紹介料や手数料は一切いただきませんので、客観的な立場からアドバイスをさせていただきます♪
定期更新の記事
ようこそ、大工村へ!
大工村はポータルサイトを介しての紹介や、主催している各種イベントなどを通して、なかなか簡単には会えない腕利きの大工さんたちと出会える場所です。
今回は、大工さんとの出会いに関する質問にお答えしたいと思います!
Q.大工村で出会う大工さんに、家づくりを相談してもいいですか?
A.もちろんです!
大工村は、家作りをお考えの方々に「大工さんに頼む」という選択肢が増えてくれることを願ってできた仕組みです。
大工村に入村している大工さんと家づくりをすることになったら、もちろん、とても嬉しいですよ。最も大切なのは、お施主さんが大工村メンバーの大工さんをはじめ様々な選択肢の中から「一番頼みたいと思った人」に頼むことですから、最後の決断まで関わるところには踏み込まず、あくまで客観的な立場からアドバイスしています。
大工村.comで村長のノリさんにメールで相談してみたり、「こども上棟式」でボランティアに来ている大工さんと話してみたり、気軽に大工さんと出会えるのが大工村の特徴です。
会いにきてみて、いいな!と思う大工さんが見つかったら、ぜひご相談くださいね。
まずは大工村に遊びに来てみてください♪
お待ちしております!
ようこそ、大工村へ!
以前ご紹介した「大工村って、どんなことをしているの?」(https://daikumura.com/blog/hitorigoto/2016/08/com-16.html)という記事では、大工村の取り組みの一部をご紹介しました。
今回はその中から「こども工務店」について、詳しくご紹介したいと思います♪
「こども工務店」とは、家作りにフォーカスした職業体験です。
家作りに携わる様々な職人さんたちの仕事の体験は、周りで見守っている親御さんたちも興味深いようで、「勉強になる」という声も!
例えば大工さん体験では上棟式をしたり、外壁やさん体験では、外壁材を使って光るどろだんごやデコレーションマグネットを作ったり、瓦やさん体験では、オリジナル鬼瓦をつくっておうちに飾ることができます♪
子どもたちが楽しみながら「なりたい職業」の選択肢を広げられるよう、他にもペンキやさん体験、クロス貼り体験、左官やさん体験などなどたくさんのお仕事体験を開催しています!
スタッフには大工村のメンバーのほか、学生ボランティアさんたちも参加してくれています。学生の皆さんもぜひ、家づくりに関わる色々な職業の方と交流してみてください!ボランティア証明書も発行します♪(証明書発行にはNPO法人大工村が対応いたします)
次回のこども工務店は2016年11月12日(土)~13日(日)、ららぽーと磐田にて開催します!
詳細はこちらのFacebookイベントページ(https://www.facebook.com/events/604253186421266/)をご覧ください♪
たくさんのご参加をお待ちしています!
ようこそ、大工村へ!
家作りが順調に進み、いよいよ上棟という際には、上棟式をされる方も多いと思います。
そこで今回は、大工村が上棟式をされる方へ向けて"新たな餅まき文化"としてご提案している、「投げ餅.jp」(http://nagemochi.jp/)をご紹介したいと思います!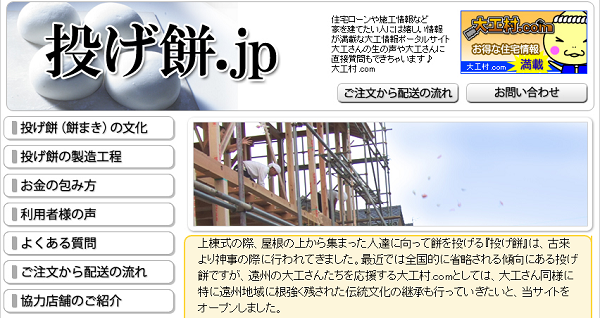
皆さんは、上棟式の儀式のひとつ「餅まき」に参加したことがありませんか?
「餅まき」では上棟の日に屋根の上に祭壇を設け、集まってくれた家族、友人、近隣の方々へ餅や銭(硬貨)をまきます。他の地域から私たちが暮らす遠州地方へ引っ越してこられた方に聞くと、この餅まきが習慣化していることを珍しく思われているようです。
また、一説によると餅まきには、「厄を避けるために餅や銭をまいて他人に持ち帰ってもらう」という意味があるそうです。
「上棟式で餅まきをやろう」と決まると、多くの方がまず餅屋さんを連想されると思いますが、餅屋さんではお餅も「俵」単位で売っていることがあり、縁起を担いで奇数俵での購入をすすめられ資金の折り合いに悩む方もいらっしゃいます。
そこで大工村がご提案しているのが、「投げ餅.jp」での「投げ餅セット販売」です!
ご近所セットのほか5万円、8万円、10万円、15万円、20万円のセットで投げ餅を販売しています。供え餅や角餅、お菓子も入ったセットです。(ご近所セットは除く)
金額別になっているので、支払額がわかりやすくて頼みやすいですね!
しかも、朝つきたてのお餅をお届けするので※、とってもおいしくいただけますよ♪
※静岡県西部にお届けの場合です。
投げ餅.jpでセットを発注しておけば、あとは銭を包んで用意するだけ!包み方は投げ餅.jpの「お金の包み方」を参考にしてくださいね♪
上棟式で餅まきをしようかな~、とお考えの方は、ぜひ投げ餅.jpをチェックしてみてください!
ようこそ、大工村へ!
NPO法人として子どもたちのキラキラした笑顔を作る活動をつづけている大工村は、たくさんの人々に支えられています。
今回は日々ご協力いただいているパートナーの皆さんの中から、「キラリ店」についてご紹介します!
キラリ店が始まるきっかけは、「大工村の手伝いをしたいけど、イベントの日はお店があってできない。何か手伝えない?」と、地元でお店を経営されている方々に声をかけていただいたことでした。
確かに、大工村が主催するイベントは多くが土曜・日曜の開催。大工村の想いに共感してくれているお店の方々の営業日と重なっていて、お手伝いを頼むことが難しかったのです。
現在、キラリ店の皆さんには、ポスターを飾ってもらったり、チラシや年に約10回発行しているダイレクトメール「クラシカル」と「わくわく新聞」を配ってもらったりと、イベントをさらに多くの方へと伝える「情報発信基地」になってもらっています。
大工村もイベントでキラリ店を宣伝したり、メルマガを利用した集客のお手伝いをしたりして、キラリ店の皆さんを応援しているんですよ。ほめる達人「ほめ達検定」のセミナーへの招待も、好評をいただいています。
◆キラリ店の一覧はこちらから!→https://daikumura.com/npo/supporter.html
大工村メールマガジン(http://www.at-ml.jp/69909/)に登録すると、特典を受けられるキラリ店もあるので、ぜひご登録ください♪
これからもたくさんの方々と大工村の想いを共有していきたいと思っていますので、色々なお店が増えていくのを楽しみにしていてくださいね!
――
キラリ店として大工村にご協力くださる方、大募集中です!すぐにご案内に伺いますので、興味のある方はぜひお問合せください♪
担当:吉見 090-6088-2347