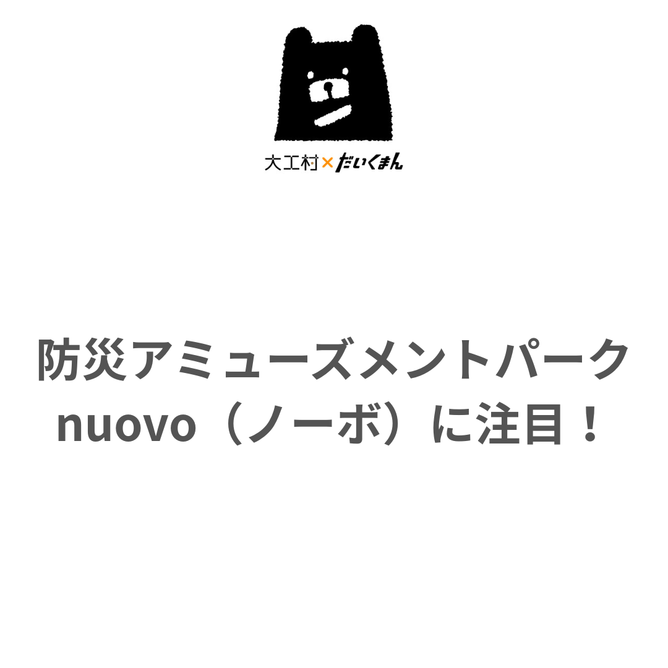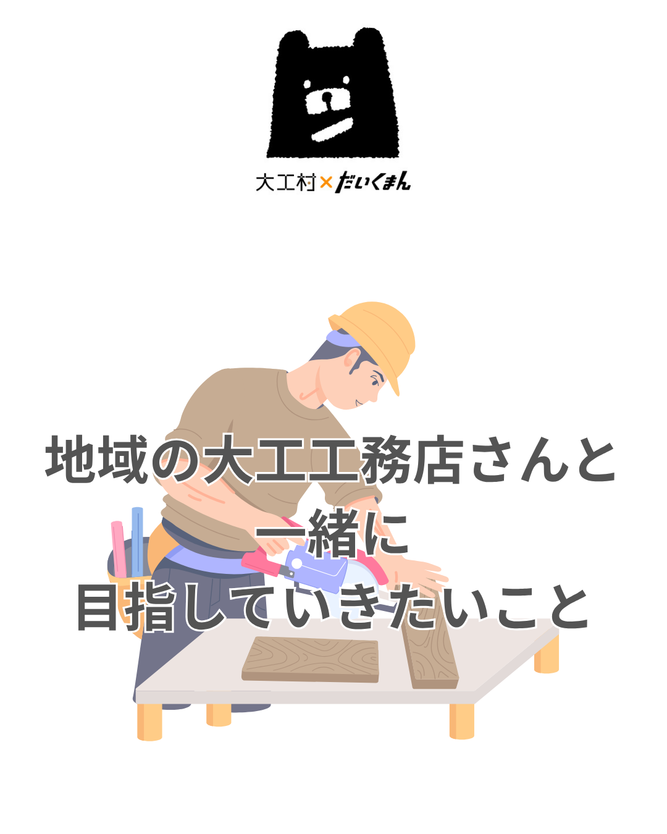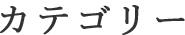こんにちは
いつも大工村の発信をご覧いただきありがとうございます。
『こども達のキラキラした笑顔をつくる!!』でおなじみ、NPO法人大工村です。
NPO法人大工村サイトはこちら♪
だいくまんプロジェクトのサイトはこちら♪
最近、家づくりを考えるご家族から
「家が高くなりすぎてしまって...」
「性能は大事だけど、うちには手が届かないかも」
そんな声を聞くことが増えました。
家の性能が良くなることは、とても素敵なことです。でもその一方で、物価高や建築費の上昇で、住まいがどんどん"高価なもの"になっているのも事実です。
静岡県西部の地域に根ざして活動してきた大工村は、「無理をしなくても、家族が安心して暮らせる家づくりができる」そんな未来を大切にしています。
・大切なのは、建てたあとも笑顔で暮らせること
家づくりは"建てた瞬間"がゴールではありません。むしろ、本当の生活はそこから始まります。せっかく家を建てたのに、ローンの返済で家族の時間が減ってしまう、教育にお金をかけづらくなる、休日もどこか気が休まらない。こんな生活では、家族の幸せが遠くなってしまいますね。
そこでお伝えしたいのが、 新築だけが「正解」ではないということです。
大工村では、地域の工務店さんと一緒に、さまざまな家の形に寄り添っています。中古住宅を購入してリノベーション、今の家を活かして性能向上のリフォーム、必要なところだけ整える"ちょうどいい"住まいの作り方など。「新築でなければ家じゃない」という時代ではありません。"家族の幸せに合う住まい"を選んでいただきたいです。
・坪単価が上がる今、どうやって家を選ぶ?
最近、坪単価の上昇スピードはとても速くなっています。性能向上の影響もありますし、世の中の動きや企業の戦略もあります。良い家が増えるのは嬉しいことですが、その影響で「普通の家庭では難しい」と感じる場面も増えました。
フラット35が1億円以上まで融資が可能になったということですが、ハウスメーカーが推奨するような高性能住宅だけが住まいではありません。家族にとってちょうどいい家を選ぶことは決して後ろ向きではなく、とても賢い選択なのです。教育や趣味や楽しみにお金とお金を使える心の余裕を持っておきたいものです。
大工村では、あくまでもお客様のペースで、あなたの家族らしい住まいを作って欲しいと思っています。物価高や建築費の上昇は、どうしても避けられない現実です。でも、だからといって「家をあきらめるべき」ではありません。地域の大工さん・工務店さんたちとともに、これからも"無理のない幸せな家づくり"をお手伝いしていきます。