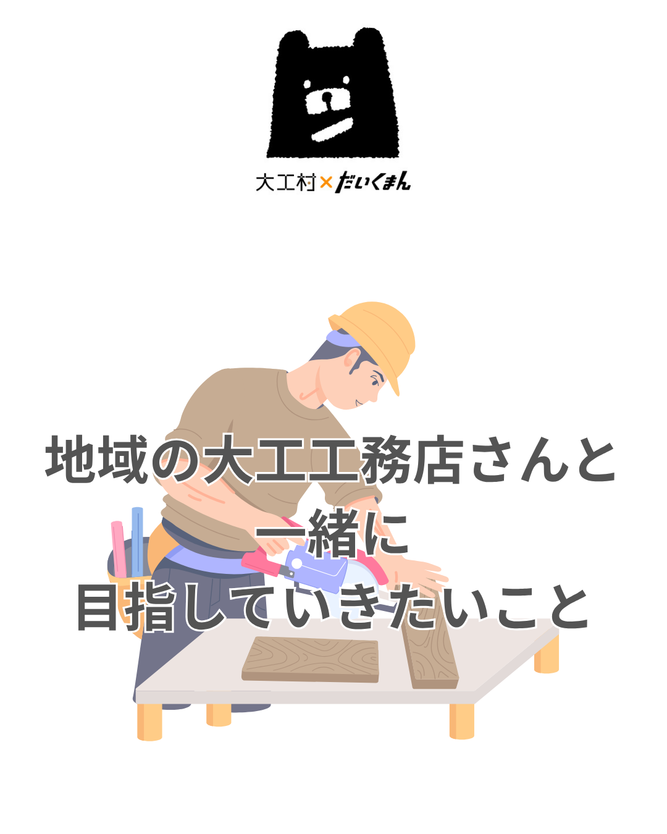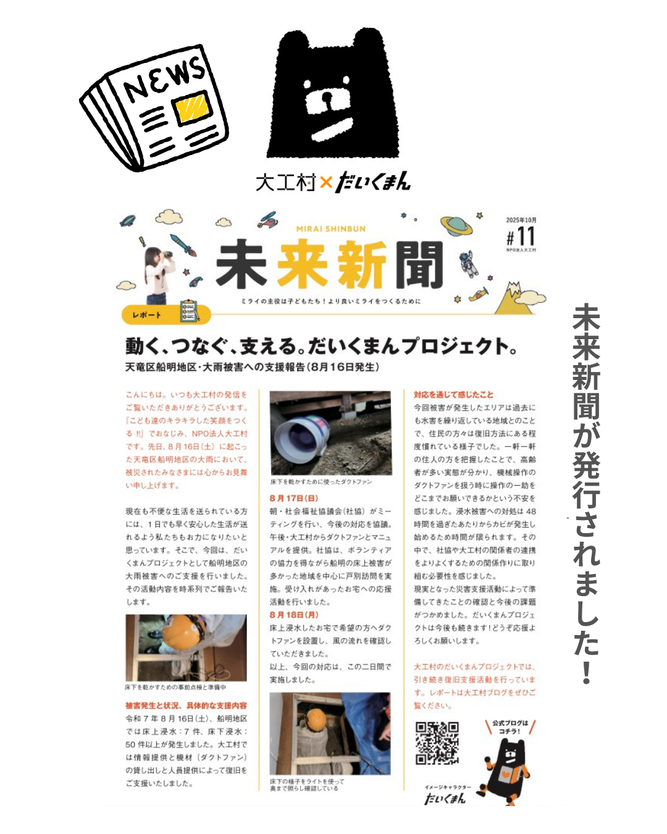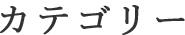こんにちは
いつも大工村の発信をご覧いただきありがとうございます。
『こども達のキラキラした笑顔をつくる!!』でおなじみ、NPO法人大工村です。
NPO法人大工村サイトはこちら♪
だいくまんプロジェクトのサイトはこちら♪
地元地域の災害復旧のため、ボランティア活動を行っている大工村のだいくまんプロジェクト。今年の水害被害での復旧活動においては、日本財団が交付する助成金を活用しました。(https://www.nippon-foundation.or.jp/)現在、大工村では交付申請のための報告資料を準備しているところになります。
助成金の交付金額は100万円。用途は、水害復旧時に各家庭の床下を乾かす際に使用するダクトファンなどの購入に活用させていただきました。このように、実際の現場で活かされる資材の購入ができたのも、大工村の技術顧問である中谷先生の指導の元、水害での被害状況の実態やその復旧に効果的なやり方を理論や経験に基づいて勉強を繰り返してきたからだと思います。
ダクトファンそのものは比較的手に入れやすい金額ではありますが、いざ被害が発生した時には1、2台といった数では間に合いません。そのため、今回助成金を利用して50台以上の購入ができ、今後の活動への備えにすることができたことは、関係者一同大きな安心材料となったと感じています。
▲ダクトファン
▲ダクトファンを始め、さまざまな災害支援品を保管しています。
こうした助成金の申請についても、専門家である中谷先生からの情報提供をきっかけに迅速に手続きを進めることができました。今後も技術指導の一貫として、水害復旧面においては実践を通じて学ぶことや新たな情報を入手することを通常の活動とし、さらに地域ごとの社会福祉協議会のみなさなと連携をはかっていきたいと思います。
大工村のだいくまんプロジェクトは、引き続き安全安心の暮らしづくりをサポートしてまいります。みなさまのご理解とご協力をよろしくお願いします。